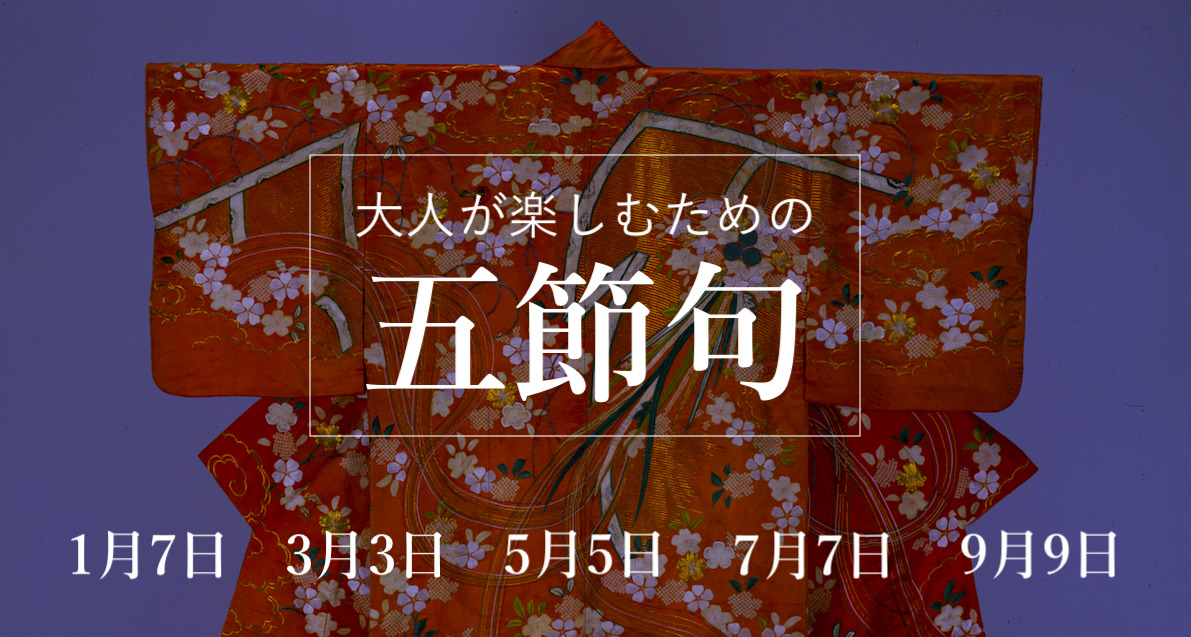

はな
無味乾燥な感じがするんです…
日本の伝統行事の雰囲気が大好きです。
ただ、本やインターネットの説明を見ても、なんだか教科書みたいで…。

はな
無味乾燥な感じがするんです…
「いいね!」といわれる暮らしを後押しするサムログとしては、
暮らしの中で楽しめないと、意味がない!
ということで
さらに、それぞれの節句の詳細ページを読んでいただけると
ようになりますので、ご覧ください!

はな
五節句とは代表的な5つの節句です
古くは室町時代からあったようですが、祝日に制定されたのは江戸時代です。そして、節句とは季節の節目のこと。
五節句とは一言でいうと、

はな
季節の節目に邪気をはらう
実にそれだけともいえます(笑)。
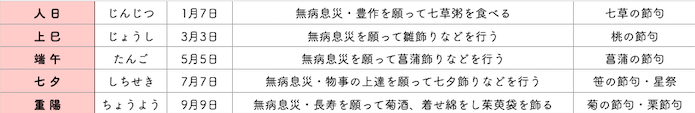
これらの節句は基本的に奇数が重なる日。
陰陽道では「奇数は陽で偶数は陰」とされてきました。つまり陽の数字が重なる日は縁起が良い日ということ。
しかし、同時に陰に傾き始める日でもあり、厄よけの出番となったようです。

はな
奇数が重なるなら11月11日は?って思いますが…
奇数だけど2桁だから該当しないんですね
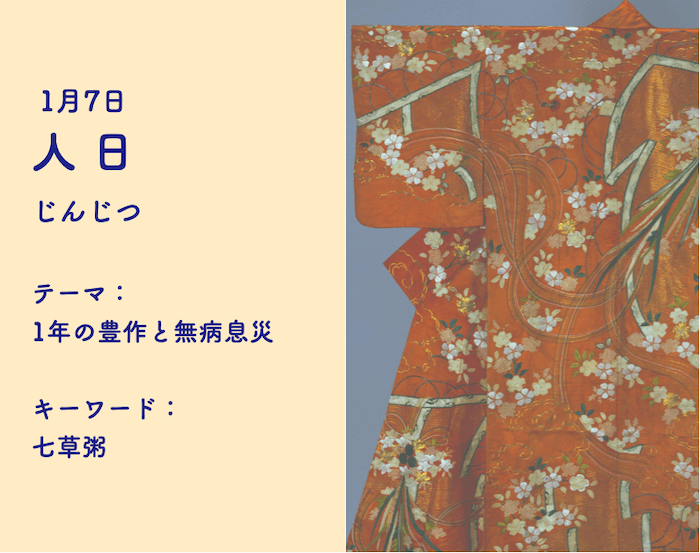

はな
いきなり奇数が重なってない!
本来は「1月1日」の元日でしたが、江戸時代に祝日と制定されたのは7日でした。
無病息災を願って七草粥を食べます。
とてもシンプル。
しかしそれだけじゃない人日の節句、詳しくは…
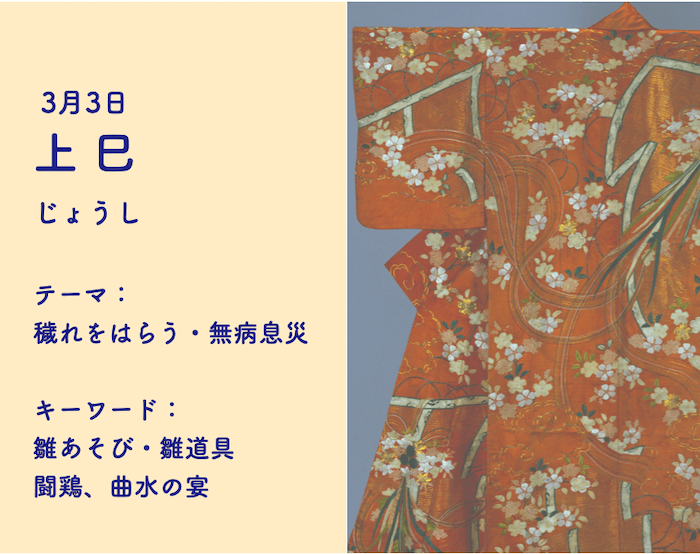

はな
日本では小さいものやミニチュアのことを
「雛」(ひな・ひいな)と表現します。
平安時代に貴族の間で「 雛 人形」を使った「 雛 遊び」が流行。
曲水の宴(当初、ケガレを人形に移して水に流す風習があった)と闘鶏(とうけい)『3月3日に鶏を戦わせる遊び』がこの雛あそびとくっつきました。
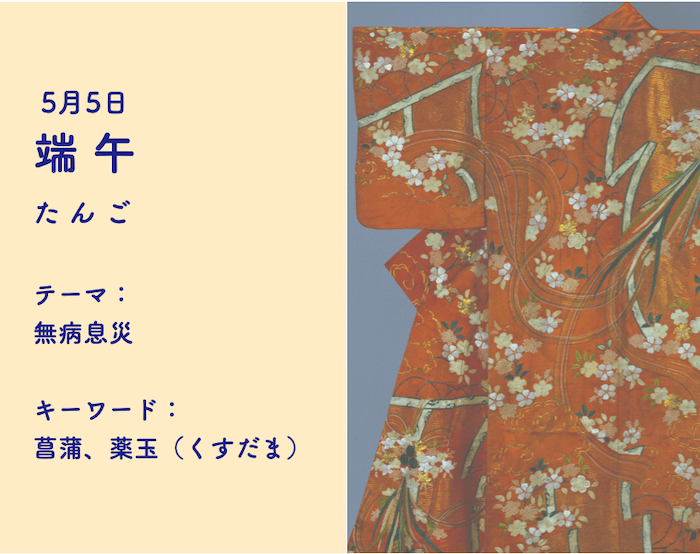
旧暦5月5日のころは、今の6月頃。

はな
梅雨の時期なので、
物がくさり、においやすい時期です
邪気をはらうために香りの強い菖蒲を飾りました。
平安時代の宮中では菖蒲を使った薬玉(セレモニーで使うくすだまのルーツ)を飾りました。

はな
ご覧ください…
薬玉とっても素敵なんです…
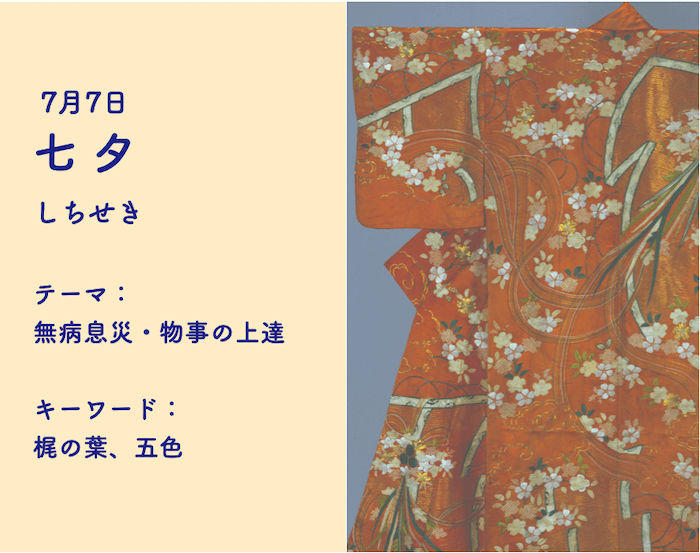
邪気払いと結びつきにくいイメージがありますが、この頃(旧暦7月)にケガレをはらう風習がありました。
乞巧奠(きこうでん)(機織りなどの上達を願う行事)、棚機つ女(たなばたつめ)伝説があわさっています。
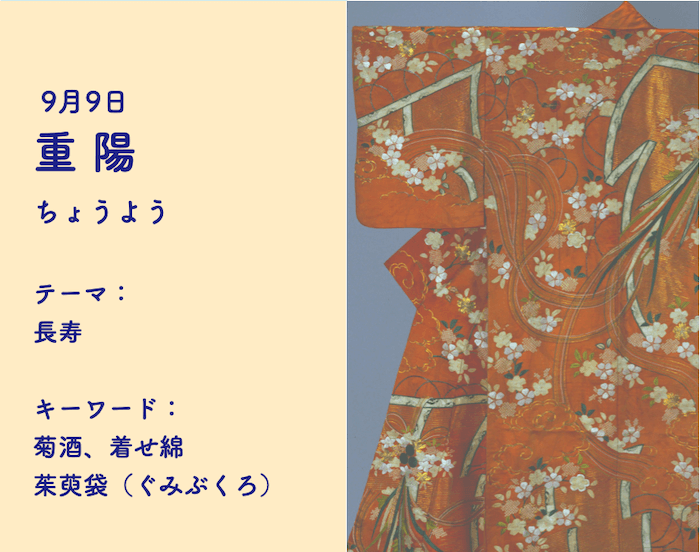

はな
まずは茱萸袋 をご覧ください!
宮中では、端午の節句の薬玉を、重陽の時期に茱萸袋へ掛け替えていました。
中国から
が伝わり、平安時代の御所の貴族たちは写真のような茱萸袋 に発展させました。
日本独自の文化である
も重陽の行事です。

はな
知名度は低いですが、一押しの行事です!
アイキャッチ写真出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/I-1077?locale=ja)

ひとり哲学「結婚しても孤独は終わらない。」
ひとりタイプ:ストイック
1986年7月19日生まれ(35歳)
趣味:和装・社交ダンス・その他
付き合い始め~結婚した後もひとり時間と二人の時間のバランスが大切です。
